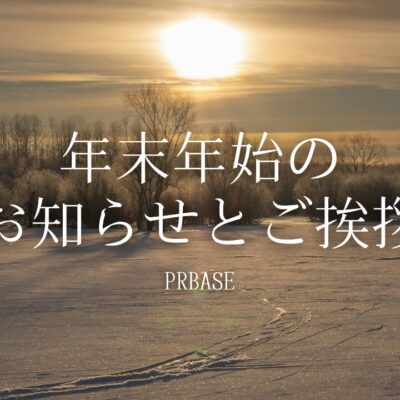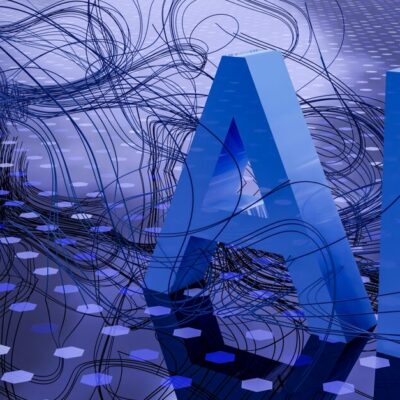いま、東京をはじめとする首都圏の都心部では、目に見えないかたちで日本人の「居住領域」が静かに浸食されつつある。かつて日本人が暮らし、働き、文化を築き上げてきた都市空間が、今では外国人投資家や旅行者によって占有され始めている。これは資本主義社会における「健全な市場競争」の結果といえば聞こえは良いが、その裏には、日本人の生活基盤が確実に押し流されているという事実がある。
まず注目すべきは、賃貸物件における違法民泊の増加だ。とくに外国人の借主によって、住居用の物件が無断で宿泊施設として運用されるケースが後を絶たない。外部からは通常の居住と見分けがつきにくいため、マンションの管理組合や近隣住民が不審に思っても証拠を掴むことは難しい。警察や自治体も対応には限界があり、トラブルが起きてからようやく動き出すというのが現実だ。このような違法民泊の横行は、賃貸住宅市場の秩序を乱すだけではない。騒音、ゴミ出し、セキュリティの問題など、居住環境そのものが悪化し、もともとそこに住んでいた日本人住民が離れていく。皮肉なことに、その空室がまた短期滞在用に転用されるという負のループが生じている。こうした事例は、渋谷区、新宿区、港区などの都心部で特に顕著だ。
一方、正規の賃貸住宅市場においても、異変は進んでいる。入居率は高止まりし、賃料は上昇の一途をたどっている。かつて10万円以下で借りられたワンルームは、今や13万〜15万円に迫り、ファミリータイプに至っては20万円を超えることも珍しくない。とくに若者にとっては、東京で一人暮らしを始めるという「人生の第一歩」が、経済的理由で選択肢から外れつつある。結婚しても状況は好転しない。二人入居可能な物件はそもそも供給が少なく、競争率も高いため、都心部ではまともな部屋を見つけることが難しい。やむを得ず築古の物件や、郊外への転居を選ぶ若者が増え、「東京に住む」という行為がもはや一部の特権となりつつある。
その背景には、もう一つの重大な構造的問題がある。それが、外国人による都心の新築分譲マンションの大量購入だ。東京湾岸エリアや都心5区の高級マンションの販売会場には、英語や中国語、韓国語など、多言語を話す営業スタッフが常駐し、パンフレットも外国語表記が標準化されている。現地での内見なしに、動画と翻訳資料だけで購入が成立するケースすらある。なぜ日本の不動産が外国人にとって魅力的なのか。理由は明白だ。日本は先進国の中でも不動産価格が相対的に安く、治安が良く、政治も安定しており、資産保全の手段として最適だからだ。さらに、日本の不動産市場には、外国人投資家に対する購入制限や所有規制がほぼ存在しない。これは他国と比べて極めて異例である。
たとえば、カナダのバンクーバーやトロントでは、外国人購入者に対して15〜20%の特別課税を課しており、実質的な参入障壁を設けている。オーストラリアやシンガポールでも、外国人購入には制限があり、自国民の住宅取得を優先する制度が整備されている。しかし、日本ではこうした規制がほぼ皆無であり、いわば「ノーガード」状態の市場となっている。その結果、都心の新築マンションは「実需」よりも「投資」が優先される商品へと変質している。空室のまま売却益を狙ったり、法人登記用として使われたり、あるいは富裕層のセカンドハウスやトランクルームとして機能しているケースも多い。こうした動きが住宅価格の上昇を加速させ、日本人が購入可能な価格帯から逸脱していく。
この流れを止めなければ、都心部に住む日本人はごく一部の超富裕層か、家業を継いだ地権者のみという時代が到来する。実際、若年層の住宅購入率は低下しており、「買える人」と「一生借りる人」という二極化が進行している。しかも、その借りる場所すら、都心ではもはや確保が難しく、郊外や地方都市への転居が促されている。つまり、首都圏の「人口の中心」は、今後も確実に外縁部へと押し出されていく。このままでは、日本人にとっての都市は、単なる「通勤のための拠点」でしかなくなり、生活の場としての機能を失う。都市は誰のものか。この問いに対して、明確な政策的メッセージが打ち出されない限り、静かな侵食は止まらない。

いま求められているのは、以下のような包括的な対策だ。
まず、違法民泊に対しては、AIやIoT技術を活用した監視・検知システムの導入が不可欠だ。たとえば、鍵の解錠履歴やWi-Fiの接続ログなどを活用し、不自然な出入りを検知する仕組みを整える必要がある。民泊禁止条項を契約書に盛り込むだけでなく、それを実効性のあるかたちで運用できる法的整備が求められる。
次に、外国人による不動産購入には、明確なルールと制限を設けるべきである。「投資目的での購入」と「実需としての居住用購入」を明確に区別し、後者には優遇策を講じつつ、前者には課税や取得制限を課す制度設計が必要だ。これは決して排他的な措置ではなく、他国がすでに実施している当然の政策に過ぎない。
さらに、若者や子育て世帯、中間層に向けた「都市部住宅支援」も急務である。低家賃・高立地の公的住宅の拡充や、シェア型住宅への補助、住居手当の拡大など、ライフステージに応じた多層的な支援策を整えることで、「都市に住み続けられる社会」の基盤を守ることができる。
私たちが本当に望んでいた未来とは、都心がグローバル資本に占拠され、日本人が追いやられる構造だっただろうか。東京や大阪が「国際都市」として発展することと、日本人の生活基盤が脅かされることは、本来、同義ではないはずだ。都市は、文化、言語、歴史、地域社会が蓄積された「生活の器」である。日本人がその中で自然に息をし、世代を超えて暮らしをつなげていくためには、居住権と生活基盤を保護する視点が必要不可欠だ。いまこそ、都市を「資本のための空間」ではなく、「人のための空間」として再定義し直すべき時が来ている。
記事提供:南総合研究所